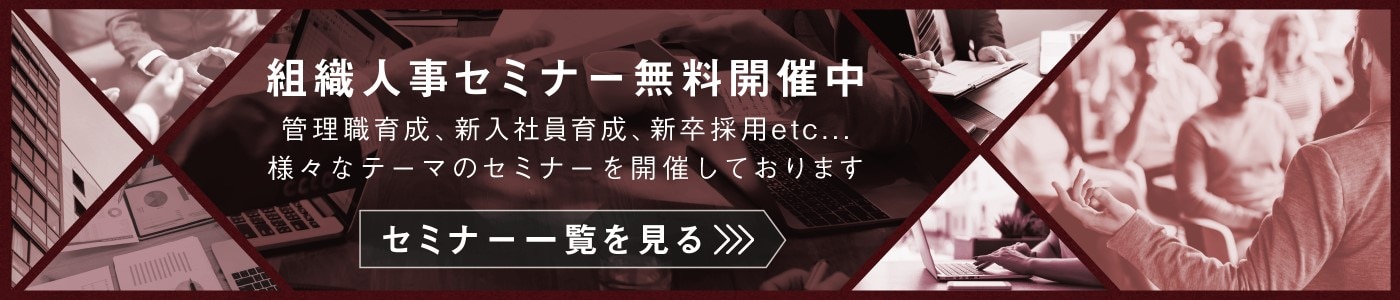2種類のダイバーシティ
~「タスク型」と「デモクラフィー型」~
タスク型ダイバーシティ
タスク型ダイバーシティでは、能力や知識、過去の経験や価値観など、目に見えない内面の多様性が求められます。変化の激しいこの時代、法規制の変更、業界再編、技術革新などの企業を取り巻く環境は大きく変化しています。(「VUCAワールド」と呼ばれます)
従って、これまでの競争優位性や顧客価値、仕事の仕方がこのまま通用するとは限りません。企業としても、個人としても、「勝ちパターン」を一通りではなく複数持ち合わせておくことで、環境変化に合わせて柔軟にスピーディに適応していくことが求められています。
デモクラフィー型ダイバーシティ
デモクラフィー型ダイバーシティでは、性別や国籍、年齢など属性を越えた多様性が求められます。日本国内の労働力の減少に伴い、これまで以上に性別・国籍・世代を超えた戦力の確保・能力開発が経営課題になってきます。
これまでのビジネスのマジョリティを担っていた「男性」「正社員」以外の属性の従業員から貢献を引き出し、組織成果に繋げていくことが求められています。企業内では「女性活躍推進活動」「外国籍社員の採用」に代表されるマイノリティの活躍を支援する施策に注目が集まっています。
ダイバーシティ=多様化=「ちがい」を許容するだけでなく、同じ方向に束ねることで企業成果に結びつけていくことが「インクルージョン」として何より大事なことなのです。
リンクアンドモチベーションが考える
ダイバーシティ&インクルージョンとは
多様性を束ね、成果創出を
コンセプトだけでなく、実践的手法を
企業組織は、組織を成立させるための3要素(チェスター・バーナード)をベースに、職場で具体的に使える観点やスキルを提供します。ダイバーシティ推進(ダイバーシティ&インクルージョン)のベースには、態度変容を促す「モチベーションエンジニアリング(行動経済学・組織システム論)」と「異文化コミュニケーション(論)」のメソッドが凝縮されています。
ダイバーシティ&インクルージョンの現状
ダイバーシティ推進の現状(言動)
~経験のある特定領域では、短期成果に貢献できる~
- 外部環境変化に疎く、イノベーションを生み出せていない
- ミレニアル世代、外国人、女性の部下を持て余している
- 短期成果に向けた効率を優先し、自分で作業してしまう
ダイバーシティ推進の現状(マインド)
~成功体験への自信と、制約への不満が根強い~
- 現事業における成果創出方法は自分が一番知っている
- 自分が育った環境を部下に提供することを念頭においている
- 新規入社者の人材のレベルが低下していると感じている
ダイバーシティ推進の目指す姿(言動)
~多様性を束ね、組織成果に繋げられる~
- 現事業を取り巻く環境変化へアンテナを張っている
- 多様なアイデアを歓迎し受け止め、客観的な評価ができる
- 多様なモチベーションの充足と組織成果を両立させられる
ダイバーシティ推進の目指す姿(マインド)
~違いを価値と捉える「客観性」が持てている~
- 過去の勝ちパターンへの健全な疑い(危機感)を持っている
- 自分と他人(部下)は異なることを前提として理解している
- 異なる意見を「優劣」ではなく「違い」として捉え興味が持てる
ダイバーシティ推進(ダイバーシティ&インクルージョン)
で陥りがちな壁
陥りがちな失敗①:「理解の壁」
陥りがちな失敗①:「行動の壁」
リンクアンドモチベーション
ダイバーシティ&インクルージョンコンサルティング
のポイント
- 多様性に対応する必要性の真の理解:概念として捉えがちな「ダイバーシティ対応」をより自分事化させ、これまでのマネジメント経験を改める機会を提供します。
-
「ダイバーシティ」の概念整理:日本企業におけるダイバーシティマネジメントの過去と現状やダイバーシティ&インクルージョンの本質的な目的の理解を促します。
- 「インクルージョン」の具体的スキル付与:組織を束ねるための考え方をわかりやすくフレームワークとして提示し、具体的な事例をもとに理解を促します。
リンクアンドモチベーション
ダイバーシティ&インクルージョンコンサルティング
のプログラムの流れ
ダイバーシティマネジメントの必要性への共感
実践的なフレームワークやスキルの習得
リアリティある属性を考慮した対応演習
受講者の声
- ダイバーシティ推進が企業に求められる理由・背景を正確に理解することができ、中期経営計画の達成に向けてその推進が不可欠であることが腹落ちしました。
- 何故会社がダイバーシティ推進に取り組んでいるかなど根本的な概念を確認できたこと、周辺環境が大きく変化している事をあらためて実感出来たことなど、非常に有意義でした。
- ワークやロールプレイが入り、ダイバーシティについて具体的に考える事が出来ました。ケースワークは日常業務の中で起こりうる内容であり、非常に参考になりました。
- 部下との関わり方について今一度考えなければいけないと痛感しました。今までの上司と部下の関わり方として、この人にはこれが最善と上司としての思い込みもあるのではと考えさせられました。継続的に話をする機会をつくっていきます。
- 今まではダイバーシティとは見た目や特徴等を受け入れることだと思っていましたが、能力や経験なども含めた多様性でありそれを活用することだということがわかりました。
- ダイバーシティに関してはLGBTなどの目に見える違いだけでなく目に見えない違いも考えると全員が対象であり目指す状態として求められる「メンバー1人ひとりのことをしっかりと把握・理解する」必要性を認識しました。
- 多様性を受け入れるという考え方から、多様性を活用することにより成果を上げる方向へと発想の転換をしていくということに大変共鳴しました。
■リンクアンドモチベーションの研修の特徴は?
弊社では2001年より、企業に対するコンサルティングで培った ノウハウやセオリーを定式化し、教育研修を開発しています。 実際の職場での活用・実践を前提とした内容に加え、 体感型ゲームやグループワークなどを中心とした “楽しみ”ながら“学ぶ” 体感型の「エデュテインメントプログラム」 となっていることが特徴です。 また、弊社の基幹技術である モチベーションエンジニアリングを用いることで 単なる知識提供や意識変革ではなく、 参加者の「行動変革」を実現する研修となっています。
■研修プログラムの種類はどんなものがある?
「新入社員研修」や「管理職研修」といった階層別の研修から 「リクルーター研修」や「営業力強化研修」といったテーマ別の研修まで 企業様のニーズに合わせて幅広く実施しております。
■プログラム内容について相談することは可能?
可能です。 リンクアンドモチベーションの研修プログラムは、 企業様のご状況・ご要望に合わせてカスタマイズし、 ご参加者の行動変化が促進されるような 最も効果的な形でご提供させて頂いております。
■研修プログラムの費用はどの程度?
研修内容・実施人数によって費用は大きく異なります。 詳細は、お問い合わせページよりご相談下さい。
■研修プログラムの実施事例はある?
様々な規模・業界の企業様にサービスをご提供しております。 詳細は、実施事例ページよりご確認下さい。
あなたの組織課題や目指すべき未来から最適なソリューションを
ご案内させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせをお願いします。
ダイバーシティ&インクルージョンコンサルティング 導入事例
関連サービス
経営理念(企業理念)浸透コンサルティング

職場改善コンサルティング

育成・教育体系構築コンサルティング

人事制度設計・構築コンサルティング

経営戦略(中期経営計画)浸透コンサルティング

インナーブランディングコンサルティング
注目サービス
新入社員研修
管理職研修の内容と目的は?マネージャー等の管理職に必要な能力
お問い合わせ
世界初の「モチベーション」を切り口としたコンサルティング会社です。
創業以来20年以上にわたり、2000社以上の様々な規模・業態の企業様をご支援してきました。
経営学、社会システム論、行動経済学、心理学などの学術的成果をベースに、
組織人事領域における様々な変革のご支援を行ってきました。
貴社にとっても最適なソリューションをご案内させていただきます。
まずはお気軽にご連絡ください。
Copyright© 2018-2021 Link and Motivation Inc. All Rights Reserved