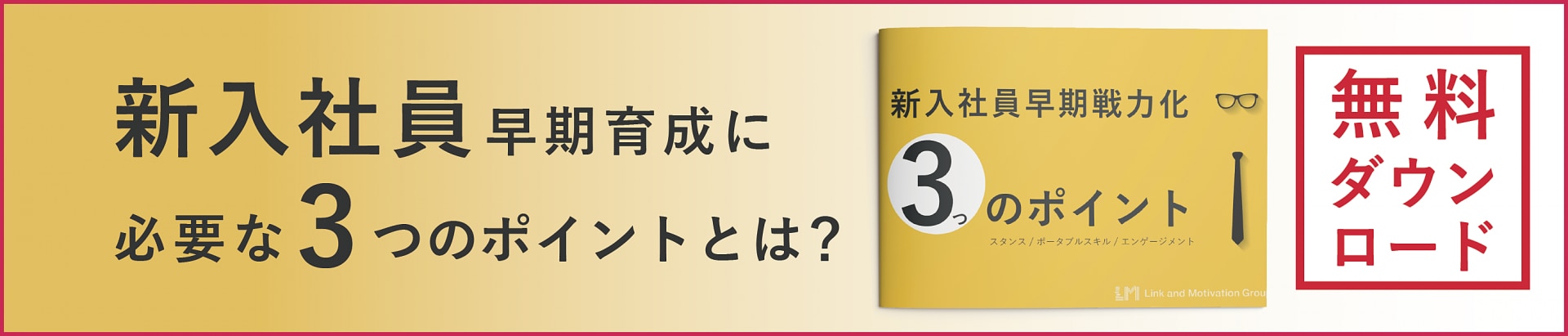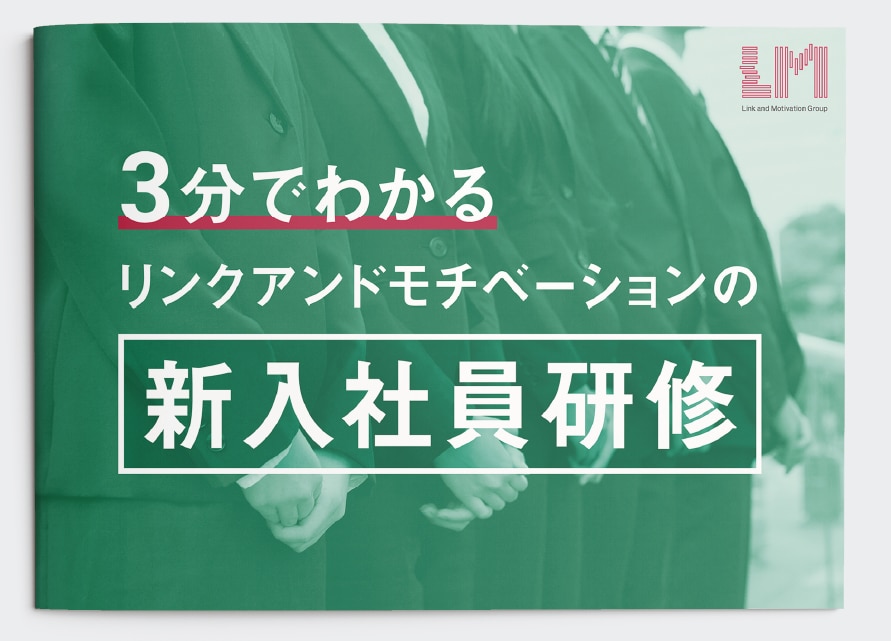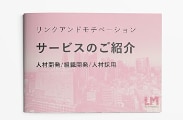「ビルを、まるごと、心地よくする」ためにトータルビルシステム事業を展開するM社。入社3年目を向かえた社員を対象に、ビジネスパーソンの基本を認識させるべく新人社員フォロー研修を導入した理由を人材開発センターのS氏に伺いました。
新人社員フォロー研修を導入した理由は何でしょうか?
無料体験セミナーに参加し、「モチベーション」というコンセプトに惹かれたのがきっかけでした。 弊社でも以前から研修を行ってきたのですが、やるべき事をやれるようにする「能力開発」にウエイトを置いていました。つまり社員一人ひとりのMUST(役割・期待)の輪とCAN(能力)の輪の重なり部分を広くする「能力開発」を目的とした研修を行ってきたのですが、期待以上の成果が思うように出ていませんでした。
どこに原因があるのか探していたところ、セミナーにて、3つ目の輪〜WANTの存在を知りました。このWANTが自立や主体性を生み、他の2つの輪との重なりに相互作用を生みだす〜そのメカニズムこそが「モチベーション」だと思い、導入することにしました。
入社3年目を対象にした理由は何でしょうか?
昔の格言で「守・破・離(しゅ・は・り)」という言葉があります。1、2年目は、先輩のやり方を真似して基本を「守」っている時期だと思いますが、3年目以降は、自分なりのやり方を見つけ出して殻を「破」っていかなければなりません。
そして、やがて完全に自分のやり方を確立するという「離」へと繋げるための重要な節目が3年目と考えていました。仕事にも慣れてきて、将来のキャリアプランや人生を考えるこの時期がモチベーションを向上させる一番よいタイミングと思い、入社3年目を対象に実施しました。
新人社員フォロー研修に期待したことは何ですか?
事前に同僚(先輩)から本人、上司から本人への2種類のメンバーシップサーベイを実施しました。その結果、傾向として「周りの人への働きかけ」が少ないことが分かりました。つまり、周りからどう思われているのか、どのような期待をされているかを理解し、自分から働きかけて期待に応えていく主体性に欠けているわけです。これを解決するためには知識の付与ではなく「意識改革」が必要です。その手だてとして自分の強みや弱み、やる気が沸くときの要因を理解し、モチベーションを自力でコントロールできるようになってもらうことが研修のねらいでした。
またサーベイを行うことで、上司の部下に対する育成意識を高めることも目的でした。上司は部下の鏡ですから、部下の弱点は、ある意味上司の弱みでもあるのです。3年目の社員とともに、マネジメントする側に対しても意識改革を促すことも期待しました。
この研修は、自己分析を通して、どのようなときにやる気が生まれるのか、下がってしまうのかを 「モチベーション曲線」として理解するところからはじまり、その上でサーベイのフィードバックを行いました。自分が思う強み・弱みと、同僚や上司が思う長所・短所が食い違っていることも多く、ショックを受けたことが逆に変革を促すことにつながったようです。
そして、最後に各自目標を設定させ、強くコミットメントさせたところがさらに良かったですね。今までの研修では一人の講師が全員に対して確認をとる(コミットメント)ことが出来なかったのですが、この研修では、グループワークを多用し、講師の他にコーディネーターと呼ばれるグループごとの指導員を配置してもらっていたので、受講者の本気度を上げられるよう、マンツーマンで確認できました。
受講後、どのような変化が生まれましたか?
今までは、仕事に対して「やらされ感」のようなネガティブな意識があったようでしたが、MUSTにWANTが加わったことで、「やりたい」「やろう」というポジティブな意識、つまり仕事への意欲が出てきたようです。
この研修を通して得た「意欲」が、仕事の効率化を加速させ、積極的に問題解決を図る意識が芽生えはじめたようです。また上司側も育成する意識が生まれ、部下が成長する環境も徐々に整ってきた感じがします。この研修をきっかけにして社内コミュニケーションがさらに促進され、組織が活性化することを期待しています。
最適なソリューションをご案内させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせをお願いします。
関連記事
あなたの組織にも、課題はありませんか?
関連サービス

ビジネスマナー研修

ビジネススタンス研修(新入社員向け)

ビジネス実践研修

360度評価研修(新入社員向け)
Copyright© 2018-2021 Link and Motivation Inc. All Rights Reserved