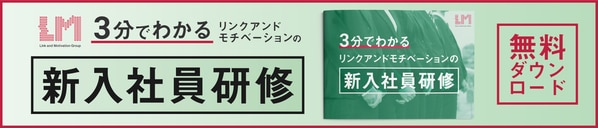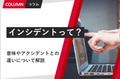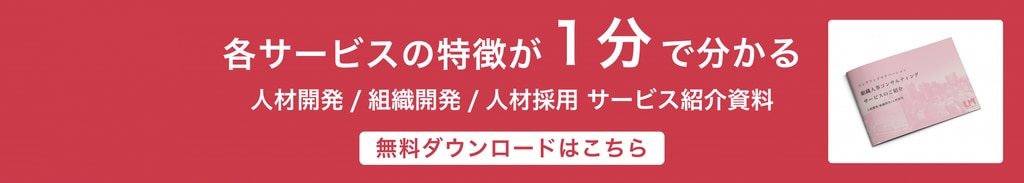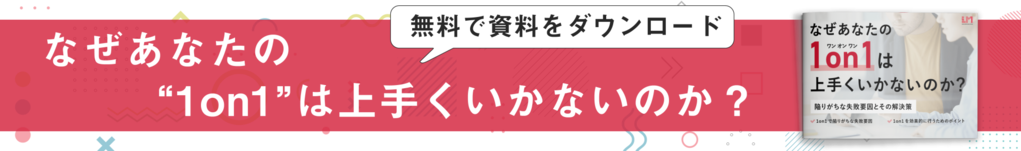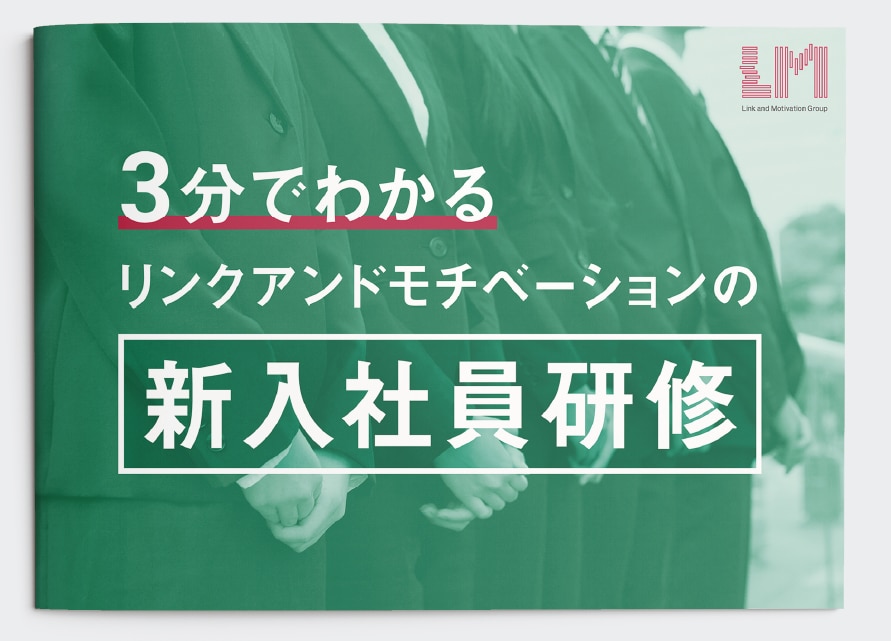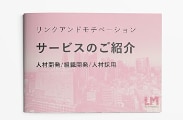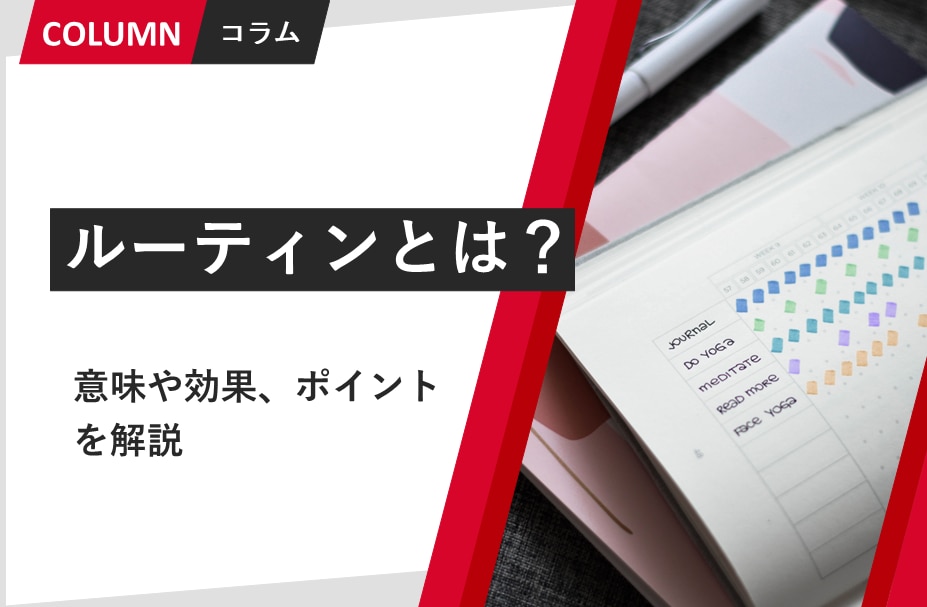
ルーティンとは?意味や効果、ポイントを解説
仕事で安定した成果を出したいと考えている方におすすめしたいのが「ルーティン」です。
ルーティンとは、決まった所作・動作を繰り返すことで、「日課」とも言い換えることができます。ビジネスの世界はもちろん、スポーツの世界などでも、第一線で活躍している人は何かしらのルーティンを実践しているものです。
今回は、ルーティンの意味や効果、ルーティンを定着させるポイントなどについて解説していきます。
▼【リンクアンドモチベーションの新入社員サービス】が分かる資料はこちら
ルーティンとは?
ルーティンとは、決まった所作・動作を繰り返すことで、「日課」とも言い換えることができます。「寝る前にストレッチをするのがルーティンだ」「その業務はルーティンにしたほうがいい」といった使い方をします。ルーティンの具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
・朝起きたら5分間、日光浴をする
・仕事前に一杯のコーヒーを飲む
・寝る前にリラックスできる音楽を聴く
・プレゼンの前に3回、深呼吸をする
毎日欠かさないルーティンを持っている人もいれば、「○○するときは必ず△△する」といったルーティンを持っている人もいます。ルーティンを取り入れることで「平常心を保てる」「緊張が緩和する」「集中力が高まる」など、メンタルに好影響をもたらし、仕事でも安定した成果を出しやすくなると言われています。
なお、「ルーティン」は「ルーチン」や「ルーティーン」と表記されることもありますが、英語「routine」のカタカナ表記がばらけているだけで意味の違いはありません。
ルーティンの効果
集中力が高まる
ルーティンを取り入れることで、集中力アップが期待できます。たとえば、重要なプレゼンの前に深呼吸をしたり瞑想したりするのは、集中力を高めてプレゼンを成功させるためのルーティンだと言えます。
オン・オフの切り替えができる
仕事にメリハリをつけたいときや、オンとオフを明確に切り替えたいときにもルーティンは有効です。たとえば、ストレッチをしたり、コーヒーを飲んだり、今日やるべきことを全部紙に書き出したりすることで、仕事のスイッチを入れるという人は少なくありません。
不調やトラブルを察知できる
ルーティンは基本的に毎日繰り返すものです。たとえば、散歩やスクワット、瞑想など、毎日繰り返してきたルーティンが、その日に限ってうまくできなかったり、感覚がいつもと違っていたりしたら、何らかの不調やトラブルが隠れているかもしれません。毎日同じ行為をすることで、ちょっとした異変のサインに気付くことができるのはルーティンの一つの効果だと言えるでしょう。
習熟度を高められる
ルーティンによって特定の行為を毎日おこなっていれば、日に日に習熟度が高まっていきます。たとえば、英字新聞を読むというルーティンを1年続ければ、確実に英語力は高まるはずです。また、ルーティンとしてストレッチを長期間続けていれば、関節の可動域が広がるだけでなく、疲れにくい体になることも期待できます。
また、毎日小さなことでも「何かに取り組むことができた」という達成感を味わうことは、自己効力感の向上にも繋がります。自己効力感が高まると、継続力がより高まり、「ここまでの予定だったけど、もう少しやろうかな」などと毎日の取り組み量自体が少しずつ増えていくきっかけにもなります。
どんな行為・動作かにもよりますが、上記の効果によって習熟度を高められるのはルーティンの効果の一つです。
ルーティンを定着させるポイント
タイミングと場所を固定する
ルーティンを定着させるためには、タイミングと場所を固定することが重要です。たとえば「毎朝7時にリビングでコーヒーを飲む」「始業時間の10分前にデスクに座り、1日のタスクを整理する」といったルーティンは、より定着しやすいルーティンだと言えます。
スモールステップで進める
スモールステップで進めることも、ルーティンを定着させる秘訣です。「毎日1時間のランニング」など、ハードルの高いことをルーティンにすると定着させるのが難しくなります。最初は「毎日10分のウォーキング」など、「スモール」で始めて、徐々に時間を延ばしたり範囲を広げたりしたほうが定着しやすくなります。
最低でも2ヶ月は継続する
ロンドン大学のフィリップ・ラリー博士らの研究によると、新しい習慣が身に付くまでの平均日数は「66日」だと言われています。そのため、新たなルーティンを取り入れる際は、少なくとも2ヶ月は継続することを最初の目標にしましょう。「2ヶ月続けられることは何だろう?」という視点でルーティンを決めるのもおすすめです。
▼【リンクアンドモチベーションの新入社員サービス】が分かる資料はこちら
ルーティンの例
モーニングルーティンとナイトルーティンについて
ルーティンの中にも、様々な種類や内容があります。よく取り上げられるモーニングルーティンとは文字どおり「朝のルーティン」で、ナイトルーティンは「夜のルーティン」です。それぞれの具体例などをご紹介します。
モーニングルーティン
モーニングルーティンは、朝の時間帯におこなうルーティンのこと。モーニングルーティンを設けることで、良いリズムで1日をスタートすることができます。
モーニングルーティンを取り入れる際に意識したいのが、起床時間を固定することです。日々、起床時間が異なっていると、ルーティンが定着しなかったり、定着したとしても毎日同じリズムを作るのが難しくなったりします。
モーニングルーティンとして多くの人が取り入れているのが「散歩」です。その他、「水を飲む」「コーヒーを飲む」「シャワーを浴びる」などもモーニングルーティンの定番です。
ナイトルーティン
ナイトルーティンは、夜の時間帯におこなうルーティンのこと。1日を振り返るルーティン、1日の疲れを癒すルーティン、スムーズな就寝を導く「入眠儀式」としてのルーティン、翌日に備えるためのルーティンなど、様々なナイトルーティンがあります。
ナイトルーティンとして多くの人が取り入れているのが「ストレッチ」や「読書」です。その他、「日記をつける」「音楽を聴く」「翌日の洋服を準備する」なども、取り入れている人が多いナイトルーティンです。
ルーティンワークについて
ルーティンワークとは、ある決まった業務や仕事を一定の間隔で繰り返しおこなうことを言います。イレギュラーが起きるケースが少なく、日々の業務で大きな変化が生じないことが多いです。
仕事の効率を高めるルーティンワークの例
職種によっては専門的だったり、その職種固有のルーティンワークがありますが、ここでは多くのビジネスパーソンが実践できる、仕事の効率を高めるルーティンワークについてご紹介いたします。
・【全員向け】日報の提出による内省
日報や日記を書くことで、日々内省を回すルーティンを身に着けることは効果的です。その日に自分が取り組んだ業務内容について、良かったこと/悪かったこと、なぜそのような結果になったのかという要因分析、改善の方向性を毎日考え、文字にして振り返るルーティンは、自身の業務効率の改善や成長に繋がります。さらに、チーム内で日報を共有することで、お互いの状況を把握する習慣をつくることも可能です。
・【全員向け】タスク管理
タスク管理は多くの方が行うと思いますが、必要な時に行うのではなくルーティンワークに組み込んでしまうのもおすすめです。毎朝始業するタイミングや終業するタイミングで、1日の予定だけでなく週単位・場合によっては月単位でタスクを可視化し、状況に応じてタスクの順番を入れ替えたり見込み時間を調整したりします。そうすることによって、事業成果への影響が大きい仕事からは素早く取り組めるなど、効率や生産性を高めることができます。
・【マネジャー向け】始業時のMTG
最近だと、リモートワークの会社も多く、コミュニケーション機会が減っているという職場も多いです。そのような場合は、毎日始業時にはMTGを行い、顔を合わせてから業務を開始するといったルーティンもおすすめです。始業時に顔を合わせることで、メンバーの忙しさやコンディション把握にも役立ちます。また、メンバー同士も状況がわかりやすくなるので、日中のコミュニケーション促進に繋がります。
・【マネジャー向け】定期的な1on1
週に1回など時間を決めて、定期的にメンバーと1on1を行うのも効果的です。メンバーのコンディション把握や、キャリアプランなどを話すことは、離職防止等メンバーマネジメントに役立ちます。メンバーの人数が多く、定期的に全員と1on1をするのが難しければ、毎日必ず声をかけるといったルーティンもおすすめです。
著名人のルーティン
イチローのルーティン
プロ野球選手として日米で活躍したイチロー氏は、バッターボックスに入る際、必ず同じ動作をすることで知られていました。メジャーリーグ10年連続200本安打などの並外れた成績は、このルーティンと無関係とは言えないでしょう。
孫正義のルーティン
ソフトバンクの創業者である孫正義氏は若い頃、「毎日5分、発明アイデアを考えてノートに書く」というルーティンを持っていました。このルーティンが、後の「音声機能付き電子翻訳機」の発明につながったと言われています。
村上春樹のルーティン
小説家として数多くのヒット作を生み出している村上春樹氏は、小説を書き上げるまでの約半年間、毎朝4時に起床し、それから4~5時間を執筆に充てています。執筆後は必ず1時間程度の運動をして、昼過ぎからは自由時間として、夜9時に就寝するというルーティンを持っています。
まとめ
「ルーティンで人生が変わる」と言ったら大げさかもしれませんが、ルーティンをうまく取り入れることができれば、仕事のクオリティやスピードの向上につながります。半年、1年とルーティンを継続することができれば、きっと効果を感じられるはずです。ぜひ自分に合ったルーティンを取り入れて、仕事で安定した成果を出していきましょう。
ルーティンに関するよくある質問
Q:ルーティンのデメリットは?
A:ルーティンばかりに依存していると「決まったことだけやっていればいい」というスタンスに傾いてしまい、新たなチャレンジに抵抗が生まれてしまうことがあります。また、ルーティンにこだわるあまり、イレギュラーが起きたときに臨機応変な対応ができなくなるケースもあるようです。
Q:初めてのモーニングルーティンには何がおすすめ?
A:気が向いたときにだけやる行為では、ルーティンとは言えません。ルーティンを取り入れるなら、毎日気軽にできて、無理なく続けられる行為を選ぶのがおすすめです。モーニングルーティンであれば、「起きたら水を飲む」「3分間ストレッチをする」「ベッドメイキングをする」などが手軽でおすすめです。
▼【リンクアンドモチベーションの新入社員サービス】が分かる資料はこちら